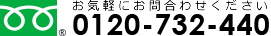目次
そもそも4号特例とは?

建築物を建てる際には、原則として建築基準法に基づいた「建築確認申請」を提出する必要があります。しかし、全ての建物の建築にあたってこの確認申請が求められるわけではありません。中には、建築士などの専門家による設計であることを前提とした上で、建築主事(または指定確認検査機関)の確認を一部省略できる建築物もあります。
この簡略化された確認制度を「4号特例」といいます。
なお、4号特例は建築基準法第6条第1項第4号に規定されていることから「4号建築物」=「4号特例対象建築物」と呼ばれています。
4号建築物に該当するのは?
この4号特例対象建築物に該当するのは、以下のような小規模な建築物となります。
【木造建築の場合】
◼︎木造建築であること
◼︎延べ面積500㎡以下であること
◼︎高さ13m以下、もしくは軒高9m以下であること
【非木造建築の場合】
◼︎1階建て(平屋)であること
◼︎延べ面積200㎡以下であること
この条件であれば、一般的な戸建て住宅や平屋住宅のほとんどは、この特例の対象になっていました。そのため、一般の建築物を新築・リフォームする際は、設計図書の審査が不要となり、手続きが簡素化されていたため工事も早く進められていました。
2025年から縮小された4号特例
この縮小の背景には、住宅の構造安全性に対する社会的な関心の高まりや、設計内容に不備がある建築物の増加があります。2025年(令和7年)以降は、4号特例の範囲が縮小され、これまで簡略化されていた木造2階建てなどの建物にも、原則として構造計算や確認申請が求められるようになりました。
このことで、以下の点で変更が起きています。
【木造建築の場合】
◼︎2階建て以上の住宅は、4号特例から新2号特例に変更され構造関係図書の提出が必要
◼︎延べ面積が300㎡を超える建築物の許容応力度計算が義務化
◼︎増築して延べ面積が500㎡を超える場合は確認申請が必要
◼︎構造に関わる壁や柱の撤去や変更、屋根の形状を大幅に変更するリフォームも確認申請が必要
◼︎防火・準防火地域内のリフォームに関しても確認申請が必要
【非木造建築の場合】
◼︎1階建て(平屋)であり、かつ延面積が200㎡以下の建築物で、審査省略ができるのは都市区域外に建築される場合に限る
さらに、新築や増改築リフォーム時に、設計者(建築士)が、建築物の構造の安全性について明確に説明できなければ、確認申請が通らないこともあり得るようになったのです。
今リフォームを検討している方がすべきこと

このため、「自宅のリフォームを予定していたのに、申請が必要になってしまうのでは?」と不安を感じられる方もいらっしゃるかもしれません。
そうした方に向けて、状況を整理するための手順についてお伝えします。
自宅が4号建築物に該当するか確認
建築確認済証や登記簿謄本、設計図書などから、構造や規模を確認しましょう。築年数が古い住宅ほど、書類が手元にない場合もあります。その場合は、市役所や法務局などで確認可能です。
リフォーム内容が確認申請の対象か判断
構造を変更しない内装リフォームであれば、確認申請は不要となることがほとんど。
しかし、耐震補強や間取り変更を伴うのであれば、申請が必要になる可能性が高いためリフォーム内容を今一度詳細に確認しましょう。
建築士や施工会社に相談
申請の有無や手続きの詳細は、専門家でなければ判断が難しいため、信頼できる建築士やリフォーム会社に相談し、必要に応じて設計・申請代行を依頼しましょう。
ナサホームでも申請が必要か否かの判断に始まり、申請代行まで対応しておりますので、お困りの際はお気軽にお問合せフォームまたはお電話でご相談ください。
確認申請が必要になった場合の申請方法

なお、4号特例の縮小に伴い確認申請が必要な建築物になった場合の基本的な手続きは以下の通りです。
設計図書の作成(建築士による)
必要書類の用意(建築確認申請書、配置図、断面図、平面図、立面図など)
管轄の建築主事または指定確認検査機関へ申請
1〜2週間の審査期間(※)を経て、確認済証が交付された後に工事着工へ
※図面作成や事前相談なども含めると1ヶ月以上の日数がかかるケースもあります。
確認申請は、代行してもらうことも可能!
4号特例の縮小に伴い確認が必要になったとしても、これからリフォームを行う施主様がご自身で申請を行うのは至難の業。なにより申請に下記のような書類を作成したうえで自治体の建築主事、もしくは民間の指定確認検査機関に提出する必要があるのです。
【申請に必要な書類一覧】
◼︎建築確認申請書(様式1号)
建物の基本情報や申請者、設計者、工事施工者などを記載します
◼︎配置図・案内図
建築物の敷地や周囲の状況を記した図面です。
◼︎平面図・立面図・断面図
リフォーム箇所を含めた建築物の詳細な設計図面です。
◼︎構造計算書
建物が安全で、地震や風などの外力に耐えられる構造を有しているかを確認するための書類です。
◼︎その他、仕様書
建築材料や構造の概要を記した書類が必要です。
◼︎確認手数料の納付書
確認申請に必要な費用を納付した際の証明書です。
確認申請は、専門的な知識が求められるため施主様が自身で行うのは現実的ではありません。現在多くの方が、建築士や設計事務所に代行を依頼しています。
確認申請の代行依頼に必要な費用は?
確認申請を、建築士やリフォーム業者に依頼するときの費用相場は以下の通りです。
◼︎木造2階建て住宅のリフォームの場合:10万円〜20万円
◼︎増築や構造変更を伴う大規模なリフォーム:20万〜30万円以上
リフォーム業者に申請代行を依頼する場合、設計費用やリフォーム費用と一緒に代行費用を支払うことになるケースもあるため、事前にリフォームにかかる全ての費用に関する見積り書の提出を依頼し、その内訳をしっかりと確認することが大切です。
まとめ
4号特例の縮小は、一見するとリフォームのハードルが上がるように感じられるかもしれません。しかし、裏を返せば「より安全で質の高い住宅改修」が求められるようになったとも考えられます。今後は、建築士の設計や安全性のチェックがより重要になってまいります。ナサホームでも、この改正に伴いより安全で快適なリフォームを提供するため、確認申請の実施とともに、多くの施主様に信頼いただける丁寧で正確なリフォームの実施に努めてまいります。現在木造建築の平屋や小規模な建築物のリフォームをご検討中の方で、確認申請にお悩みの方は、ぜひナサホームにそのお悩みのお声をお聞かせください。