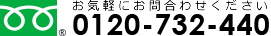目次
サイクルポートの基礎知識
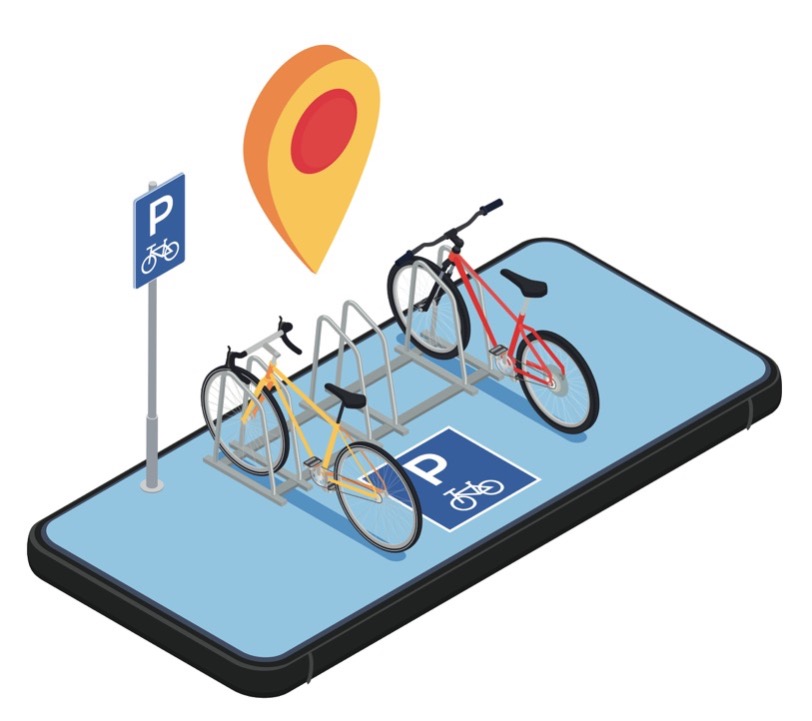
サイクルポートについて知ろう
サイクルポートは、「住まいの敷地内」に設けることができる屋根付きの自転車専用駐輪スペースで、カーポートの自転車版と考えれば良いでしょう。サイクルポートは自転車を雨や紫外線から保護することを主な目的とした設備ですので、屋根材にも機能的なものが使用されています。構造としては、金属製の支柱にポリカーボネートやスチール製の軽量屋根材を取り付けたものが主流。
サイズは自転車1〜2台用のコンパクトなものから、家族全員分の自転車を収容できる大型タイプまでさまざまなバリエーションが存在します。
サイクルポートの種類と特徴
サイクルポートは、その構造や設置方法によっていくつかの種類が存在します。
皆さんのご家庭の事情に合わせて選ぶ際の参考としてご覧ください。
◼︎屋根の形状
・片流れ屋根タイプ:片側に傾斜を持たせたスタンダードな形状で、雨水を片側に流す構造になっています。住宅の景観にも調和しやすく、使い勝手にも優れているのが魅力です。
・ 両傾斜タイプ:屋根が中央から両側へ傾斜した屋根を持つカーポートで、片流れと比べて広いスペースが必要となりますが、その分駐輪台数も多くなります。
・アール型タイプ: 屋根が緩やかなカーブを描くデザインのカーポートです。
美観に優れるため、外観とのバランスを重視したい場合に好まれます。
・ポリ塩化ビニルタイプ:1万円前後の安価で販売されているDIYで組み立てるタイプのサイクルポートです。住まいの駐車場の一角などに簡易的に設置するタイプで自転車1〜2台が駐輪できます。
◼︎屋根材
・ポリカーボネート:最も一般的なサイクルポートの屋根材です。耐候性・耐衝撃性に優れ、紫外線カット機能も備わっています。なお、耐用年数は10年ほどとなっています。
・アルミ樹脂複合板:軽量で不燃性の高い屋根材です。お住まいの地域が防火地域・準防火地域で、屋外に設置できる設備に制限がある場合におすすめです。なお耐用年数は10~15年とされています。
・スチール折板:耐候性が高く、雨漏りの心配が少ない屋根材です。ポリカーボネートに比べるとやや高価で重量があります。耐用年数は20年〜30年と長いのも特徴です。
サイクルポート役割と設置時の注意点

サイクルポートを設置するメリット
■自転車の劣化を防ぐ
自転車のサドルやフレームは、雨風や紫外線にさらされることで、錆びたり色あせたりといった不具合が起こります。特に、樹脂製の部分は紫外線劣化で破損しやすくなるほか、電動自転車やチャイルドシート付きの高価な自転車は、天候によって致命的なダメージを受けかねません。そこでサイクルポートの屋根によって天候から保護することで、長期間にわたって良好な状態を保つことができます。
■整理整頓された駐輪場で住まいの美観を保つ
自転車が乱雑に置かれることで、敷地内の美観は大きく損なわれてしまいます。
そこにサイクルポートという明確な駐輪スペースを設けることで、敷地内がすっきりと整頓され、人の目につきやすい玄関先等の美観を保つことができます。
■防犯性の向上
整理整頓されたサイクルポートが人目につきやすい場所に設置されていることで、盗難のリスクは大きく軽減します。加えてサイクルポートチェーンの設置や人感センサーライトの設置を行えばその防犯性はさらにアップします。
■日々の乗降車が快適に
乱雑に置かれた自転車置き場では、時として自分の自転車に乗るために、家族の自転車をどかして乗らなければならないなどの手間が発生します。また、屋根のあるサイクルポートの下であれば雨上がりにサドルやフレームの濡れや汚れを気にすることなく自転車に乗り込むことができます。こうしたスムーズな利用は、通勤、通学時間の時間短縮にもつながります。
注意したい点・デメリット
サイクルポートにはメリットだけでなく、いくつかの注意点も存在します。
■設置スペースの確保が必要
サイクルポートを設置するには、最低でも自転車1台分(幅60〜70cm × 奥行150〜200cm程度)のスペースが必要です。これに加えて、支柱や屋根の張り出しも考慮する必要があります。
■建築基準法上の規制(建蔽率の問題)
サイクルポートの設置場所や構造によっては、サイクルポートが建築物の一部と見なされ、敷地に対する建築物の占有割合(建蔽率)に関わってくる可能性があります。
特に都市部では建蔽率の制限が厳しいため、事前に敷地条件を確認することが重要です。
ただし、下記のような仕様である場合は建ぺい率に含めなくてよいケースもあります。
・外壁のない部分が連続して4m以上
・柱の間隔は2m以下
・天井の高さが2.1m以上
・地階を除く階数が1であること
「サイクルポートが建ぺい率に含まれるのかどうか心配…」、という場合はナサホームなどのリフォーム会社に相談し、写真などでの説明や現地調査の依頼を通して、住まいの状況を判断してもらうようにしましょう。
■設置位置によっては天候的なリスクがある
強風や積雪が激しい地域では、サイクルポートにも高い耐性が求められます。耐風性・耐雪性の等級が設けられている製品もあるため、こちらもリフォーム業者に相談しながら製品選びを進めていくことをおすすめします。
設置に伴う法的・行政的な注意点
建ぺい率の注意点と重なりますが、一定の基準を超える構造を有するサイクルポートは「建築物」として扱われ、建築確認申請が必要になることがあります。
例えば…
・屋根付きで三方向以上が囲まれている
・固定された基礎を有している
・構造高さ2.1m以上かつ面積10㎡を超える
といった条件に合致していれば、申請が必要となります。
その一方で、サイクルポートの構造が屋根だけで壁が存在しない簡易的な構造であれば、「建築物」の定義に含まれないケースもあります。
なお、この判断基準は地方自治体によって解釈や取り扱いが異なるため、設置前に地域の建築指導課などに相談してみましょう。
サイクルポートの後付け費用はどのくらい?

メリットや注意点を確認したところで、実際にサイクルポートを住まいの中に後付けリフォームする場合の費用について紹介していきます。
サイクルポートの本体価格の目安
■自転車1台分:5万〜8万円
■自転車 2〜3台分:8万〜15万円
■高耐風・高耐雪対応モデル:15万〜50万円
※メーカーや製品グレードによって価格はさらに増減します。
施工費用(工事費)
設置工事費用:8万〜15万円(基礎打ちを含む)
土地の整地や排水処理が必要な設置工事の場合:15万〜20万円
※こちらも、敷地状況によって価格は大きく上下します。正確なお見積もりをお求めの際はナサホームのお問い合わせフォームよりご相談ください。
まとめ
サイクルポートは、ただの「自転車置き場」ではなく住まいの外観、快適性、防犯性、資産価値を高める外構設備の一部。
初期費用はかかるものの、日々の自転車利用や、大切な自転車を長く乗り続けるために欠かせない設備といえるでしょう。設置の際には、敷地条件や建築基準に応じた選定と施工が重要となります。数多くのリフォームやエクステリアの増設事例を持つナサホームであれば、法令に従いつつ、皆様のライフスタイルに応じたご提案&サイクルポート設置が可能です。ぜひ私どもに、皆様のご要望をお聞かせください。